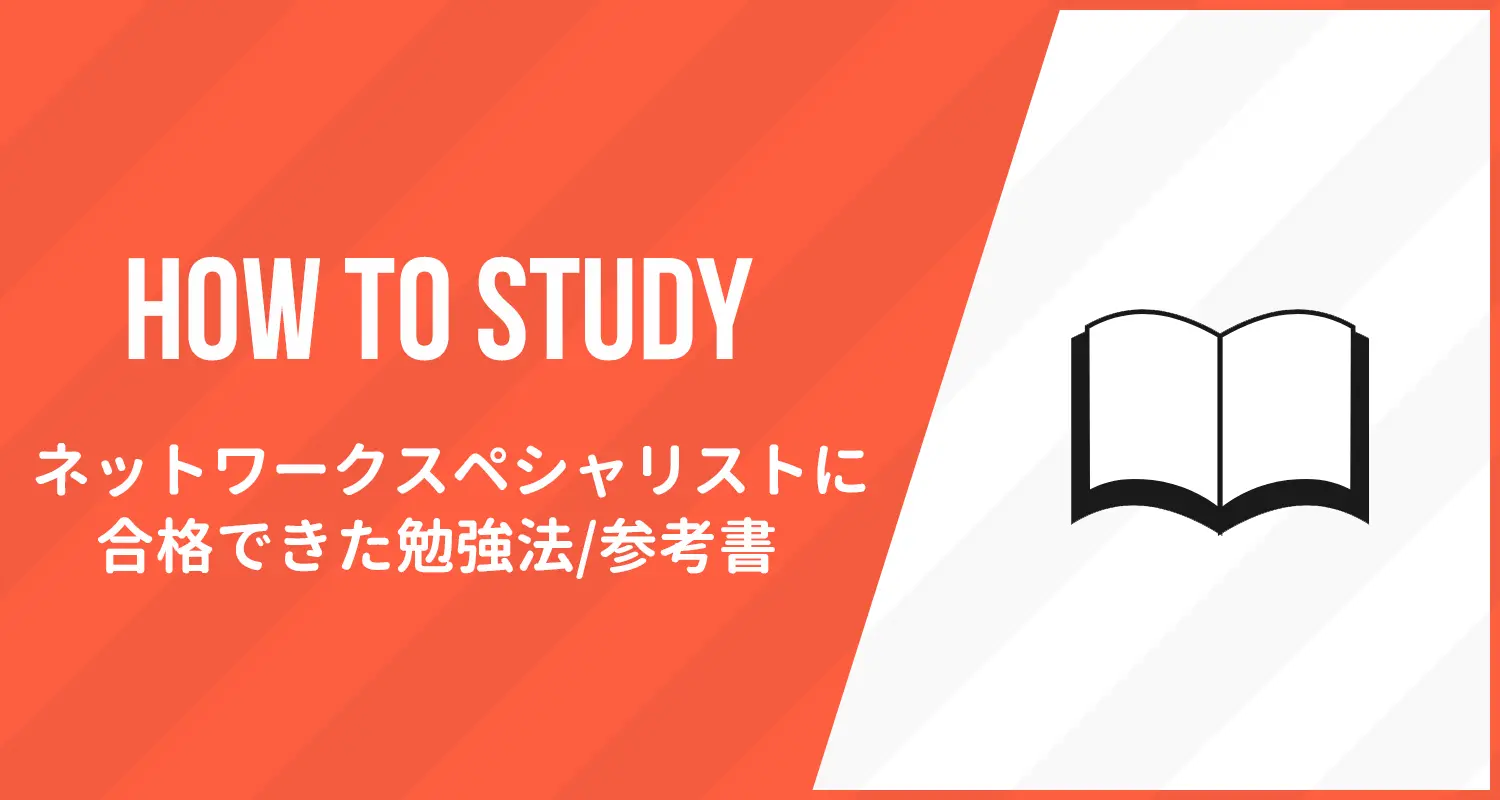- ネットワークスペシャリストに1発合格できた勉強法・参考書をご紹介
- 応用情報の延長...くらいにみてると痛い目みる
- 「知識を蓄え、解いて沈着」を繰り返そう!
毎度緊張するこの瞬間。ネットワークスペシャリスト、通称ネスペの合格発表、その当日。
震える手を抑えながら、合否ページを確認する。
結果は
- 午前Ⅰ:免除
- 午前Ⅱ:92%
- 午後Ⅰ:89%
- 午後Ⅱ:87%
無事合格できました!
当日盛大に体調を崩し、青ざめながら受験したので流石にダメかと思いましたが、どうにか合格ラインを超えることができました。
というわけで応用情報技術者試験に引き続き、次受ける方へのバトンとして、勉強法を書き残しておきたいと思います。
※書籍を2023年版に更新しました
受験前の実力
まずはサクッと僕の経歴と受験前の背景を。ここがずれすぎてると、僕のやり方に合わせても効果が薄いと思うので。
非情報系、応用情報取得済み

応用情報の記事にも書きましたが、もともと僕は情報系卒ではありません。
ですが、趣味のアプリ開発、このブログの構築・運営からITの世界にのめり込み、気づけばIT系の仕事に従事。
そこから基礎力をつけたい一心で、応用情報技術者試験を猛勉強。なんとか一発合格できています。
ネスペ受験の2つの動機
「現場で戦える知識をつけたかった」というのが第1の理由。
応用情報の勉強を終え、「よーし、バリバリ働くぞー!」と思っていた頃、ネットワークの課題が発生。
専門知識を駆使して解決に導く同僚を前に、僕は手も足も出ず、ただそこにいることしかできませんでした。
なにぶん「基礎は固めた!」という自負があっただけに、余計にまだまだ力の無さが身に沁みた瞬間でした。

また、次に取りたい資格の前段階で、ネットワークの知識が必要だったのも大きな理由。
先の話になりますが、ネスペの次は認定ホワイトハッカー試験をうけてみようと考えています。
受験前の講座で必要になる前提知識に「CCNAレベルのネットワーク知識」があったため、こちらも取り急ぎ身につけねばならず。
そんなこんなでさらなる知識をつけるため、受験に至ったネスペ試験。なので、今回も僕の勉強法は、試験に「受かる」ためというよりは「知識をつける」ための方法です。
「考えて」基礎を固めよう
ネットワークスペシャリストは
- 午前Ⅰ: 応用情報の午前試験の問題数少ない版
- 午前Ⅱ: ネットワークの選択問題
- 午後Ⅰ: ネットワークの記述問題(短め)
- 午後Ⅱ: ネットワークの記述問題(長め)
の4部構成。受験にまるっと1日かかる、なかなかにヘビーな試験です。
解いて解いて解きまくる
応用情報のときは、
- 徹底的に基礎を固めて
- 固め終わってから問題を解く
というやり方を推しましたが、ネスペはこれではたぶんダメ。
と、いうのも午後試験に
- 重箱の隅をつつくような穴埋め問題
- 基礎力では対処できない応用問題
が多いから。
なので、ネスペでは「ある程度基礎を固めたら、問題を解いて解いて解きまくる」勉強法をオススメします。
勉強時間の配分
今回の勉強期間は、トータル7〜10月の4ヶ月。
特にラスト1,2ヶ月はプライベートの全時間を注いで、過去問ならほぼ8,9割がとれるレベルまで追い込みました。内訳は、
- 7〜8月: 基礎固め
- 8〜10月: 午後試験
という感じ。
あれ?午前試験どこいった?となると思いますが、はじめて問題を解いた際に、「午前で苦戦するようなら午後は論外」だなと感じ、午前向けの勉強時間はあえて確保せず。
合格したいま振り返ってみても、午前を80〜90%取れないようでは、午後で合格ラインを超えるのは難しい、逆にいえば午後の勉強をしっかりしておけば、午前の勉強は必要ないんじゃないかなと思います。
※僕は応用情報技術者試験合格直後だったので、午前Ⅰ免除でしたが、午前Ⅰを受けなきゃいけない場合はしっかり対策しましょう(ネットワーク以外が出るので)
勉強法とおすすめの教材
では、具体的な勉強法について。
メインで使った教材は
の計5つ。プラスGoogle先生です。
ネスペの午後問題は重箱の隅をつつくタイプの問題も多いため、Google先生が必須になります。
STEP1:基礎の基礎
まずは地ならし。徹底攻略を読み込みます。
出題範囲をわかりやすく、体系的にまとめてくれているこちらの本。
もちろん中身もすばらしいんですが、それだけじゃなくて。
なんと書籍を買うと、**無料でPDF版がついてきます!**なので、状況に応じて紙でも電子でも勉強できる!
たとえば、どっしり腰を据えられる自宅では紙、荷物を減らしたい通勤時は電子といった使い分けができちゃうんです。
ほかの書籍でこれをやろうと思うと、単純に2倍お金がかかるので、このサービスは嬉しいですね。
読み方のオススメはWorkflowyにまとめながら読むことです。
Workflowyって?
ざっと説明すると「階層構造をつかえるエディタ」。といってもよくわからないと思うので、現物がこちら。
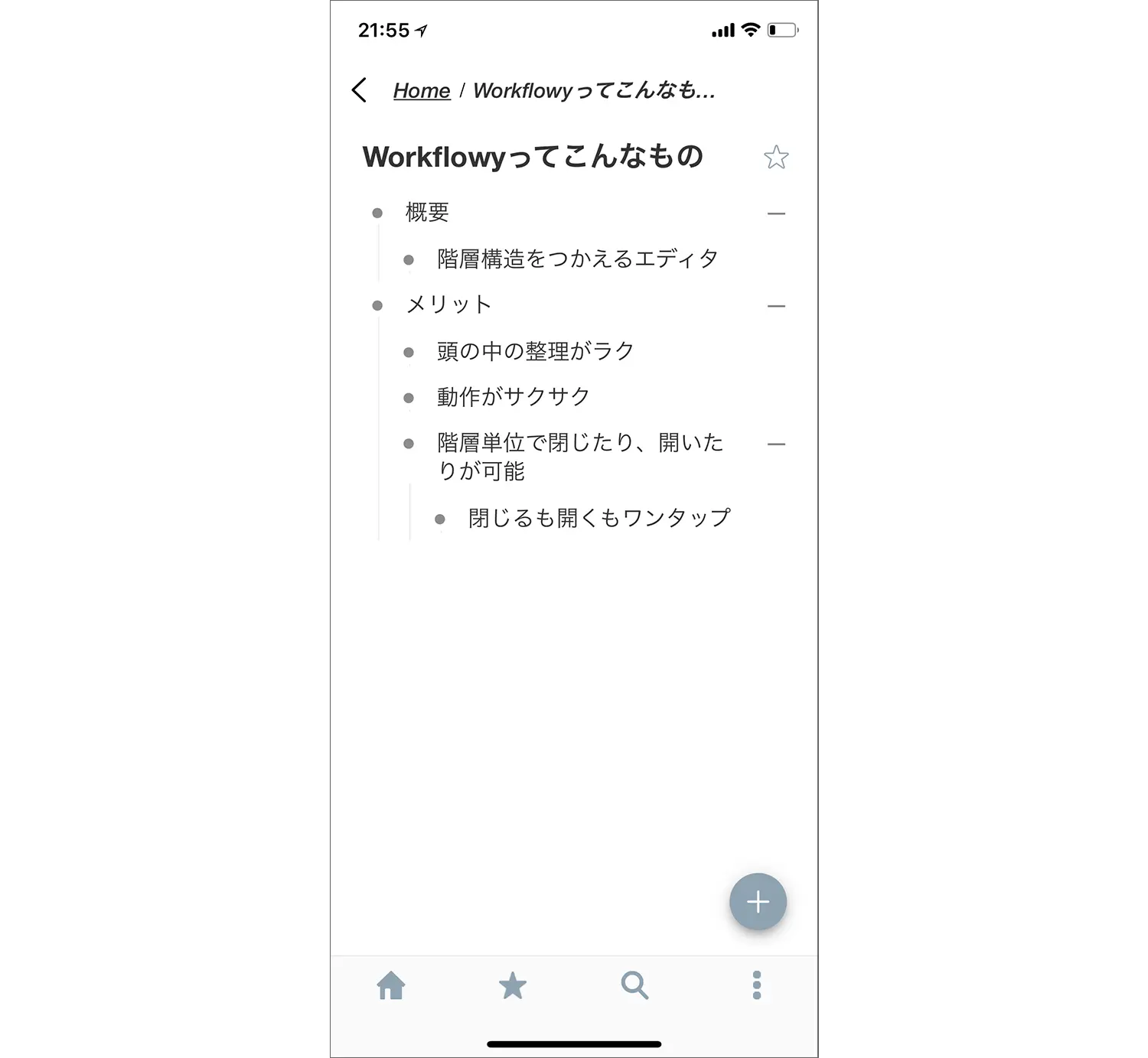
こんな具合に項目をざざざざっと書いていける軽快なエディタ。これを使って、本を1冊まるっとまとめながら読んでいきます。
【リンク】WorkFlowy公式
さらにWorkflowlyの項目を折り畳める機能を利用。閉じた状態でサクサク確認して、わからなかったものだけを展開して確認する暗記カード的な使い方で頭に叩き込みます。

僕はこのやり方で、「本と間違えた問題をまとめる→スキマ時間で反復確認」を勉強期間中ずっと続けました。このやり方がベストとはいいませんが、1日のスキマ時間って思いのほか多いので、短時間で反復できる環境を整えることが合格の肝。
他に使い慣れた折り畳めるメモツールがあればそちらでぜんぜんOKです。
STEP2:深掘りした基礎固め
概略を抑えたら、各項目をより詳しく学んでいきます。重点対策を使いましょう。
もともとは、過去問の中から選りすぐりの良問を掲載した問題集。
なんですが、各ジャンルごとに必要な知識をまとめたページをつけてくれています。
このまとめがとっても詳しくて。ほかの参考書ではパスしている、試験に出る内容を体系的にまとめてくれているので、読み込んで覚えきりましょう。
STEP3:午後問題フェーズ1
ある程度基礎が固まったらはやめに問題演習へ。STEP2と同時進行でも構いません。
ここでも重点対策を使っていきます。今度は問題部分です。
はじめは解けなくてもいいので、こんなレベルの問題が出るんだなーと思いながら解いてみてください。
基礎固めが甘いと、結構絶望すると思います。
解けなかったら、STEP1,2に戻って該当のジャンルの知識を貯める、を何度も繰り返していきましょう。
本を読んでも理解できない、載っていない内容はネスペイージスをみれば、だいたい載っています。
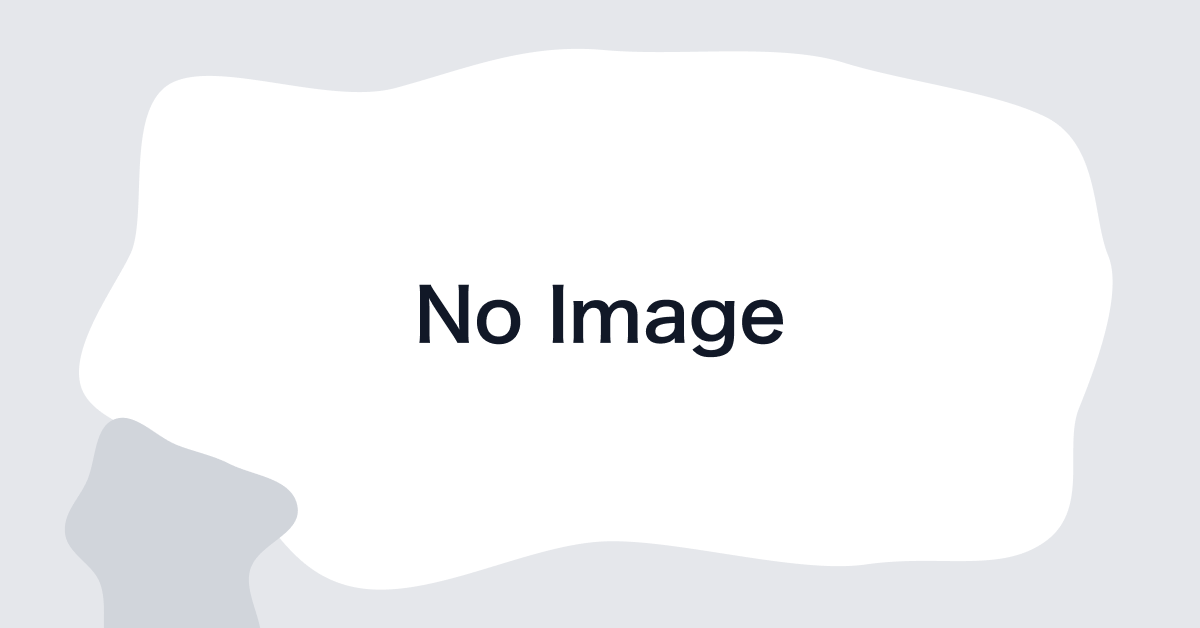
無料とは思えないボリュームと詳しさなので、有効に活用していきましょう。
STEP4:体系的に基礎を抑える
問題を1周解き終わったら、ダメ押しで基礎を体系的に固めます。ここで使うのは、左門/平田さんのネスペの基礎力。
おそらくネスペ関係の書籍で、このシリーズ以上にわかりやすいものはない!
そう断言してしまえるほどわかりやすい、左門/平田さんのネスペシリーズ。
ここで使うのは、なかでも「ある程度基礎は固めたけど、さらに磨きをかけたい」方に特化した1冊です。
「なぜ一定の時間後に、ARPテーブルから情報が削除されるのか?」のような質問+解説方式で100問以上、とてもわかりやすくまとめてくれています。
ある程度の知識があることは前提のつくりなので、過去問を1周解いたタイミングで読むのがオススメ。
補足:左門/平田さんの問題集もオススメ
左門/平田さんの本は、各年分の問題の解答・解説を載せた問題集タイプもあります。
Amazonのすさまじい評価の高さからも、質の高さが伺えます。
1冊の問題量は少ないですが、解説のわかりやすさはピカイチ。解説をめちゃめちゃ詳しくした分、各本に1年分の問題しか載せられなかったんだろうなと。
上でご紹介した重点対策の解説は、難解なところも多いので、わかりやすい解説を求めるならこちらも購入したほうがいいかと。
本音を言えば、「両方買って解説を見比べながら解く」のがベスト!
(平成28年分は、解説少なめでネスペの基礎力にくっついています)
STEP5:午後問題フェーズ2
いよいよ仕上げ!繰り返し過去問題を解いていきます。
2周目以降は「全問解けなければおかしい」ぐらいの気持ちで挑みましょう。
僕の場合は、
- 1周目: 重点対策
- 2周目: 予想問題集
- 3周目: 重点対策
を使いました。
これから挑むみなさんは
- 重点対策のみ
- 重点対策+左門/平田さんシリーズ
のどちらかを選ぶとよいかなと思います。
時間の許す限り繰り返し解いて、試験当日に備えましょう。
どれだけ解けるかが合格の鍵
ネスペ試験はスペシャリスト試験のなかでも、特に難しいものとされているようです。
実際午後問題は、「覚えれば解ける基礎問題」でなく、「その場で考えなければ解けない応用問題」ばかりなので、難しいとされるのかもしれません。
なので、合格の鍵は自力で考えに考えて、解答を絞り出す経験をどれだけ積めるかにかかっています。
言いかえれば過去問を解いた数が合格に直結するってことです。
少しでも多く、問題を解く。これを念頭にがんばってみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
どんぎ(@_Donngi)でした。